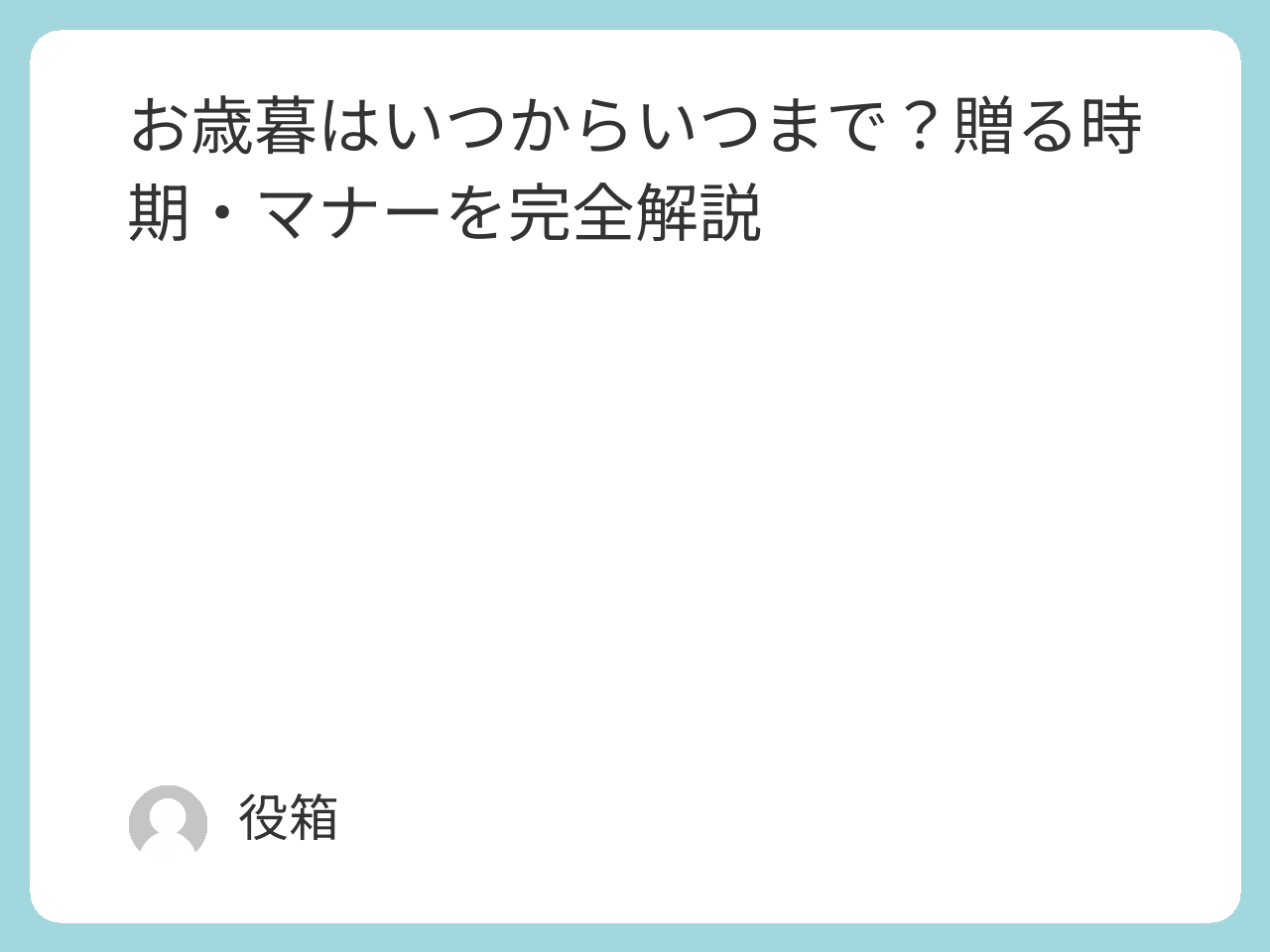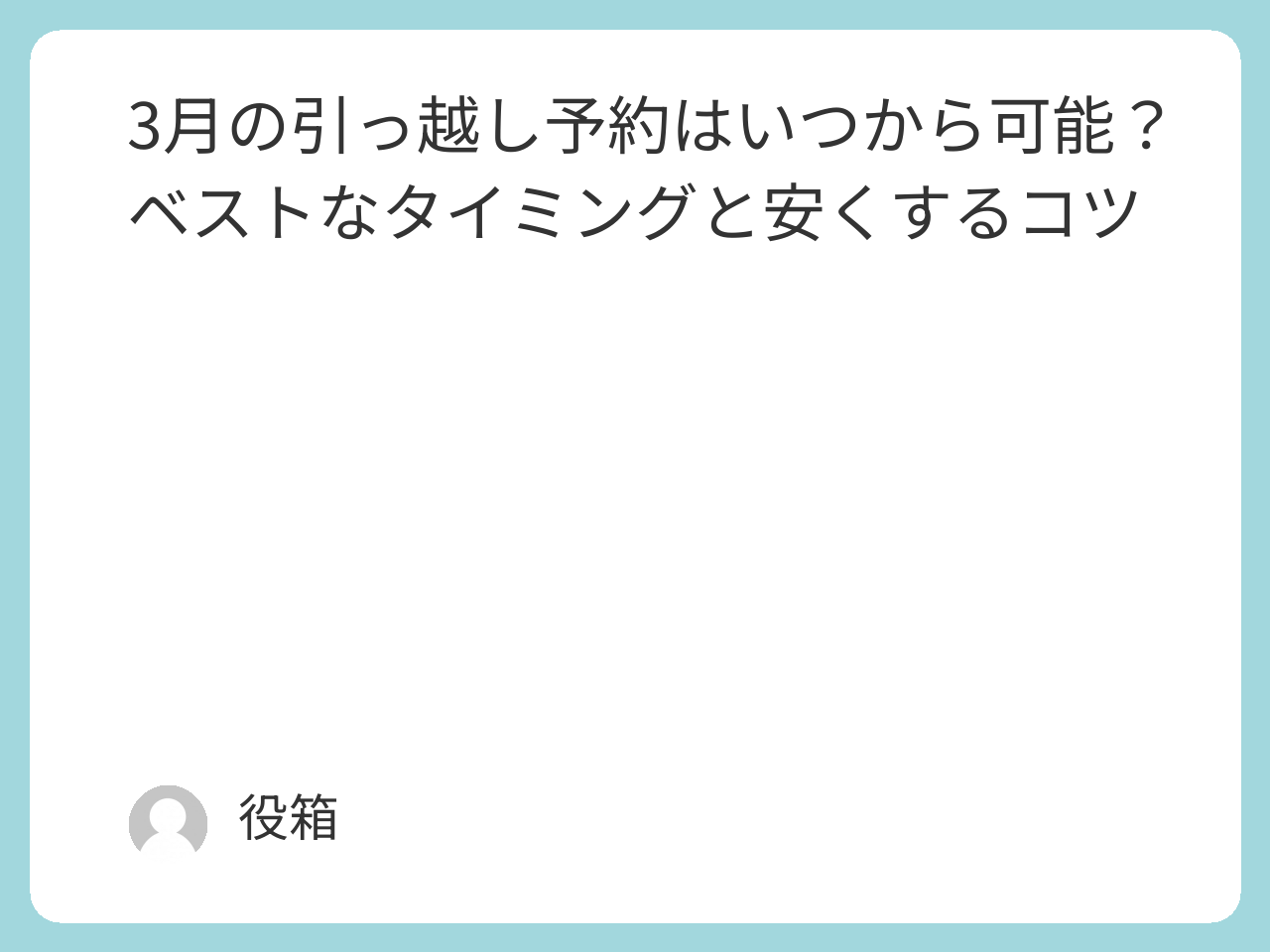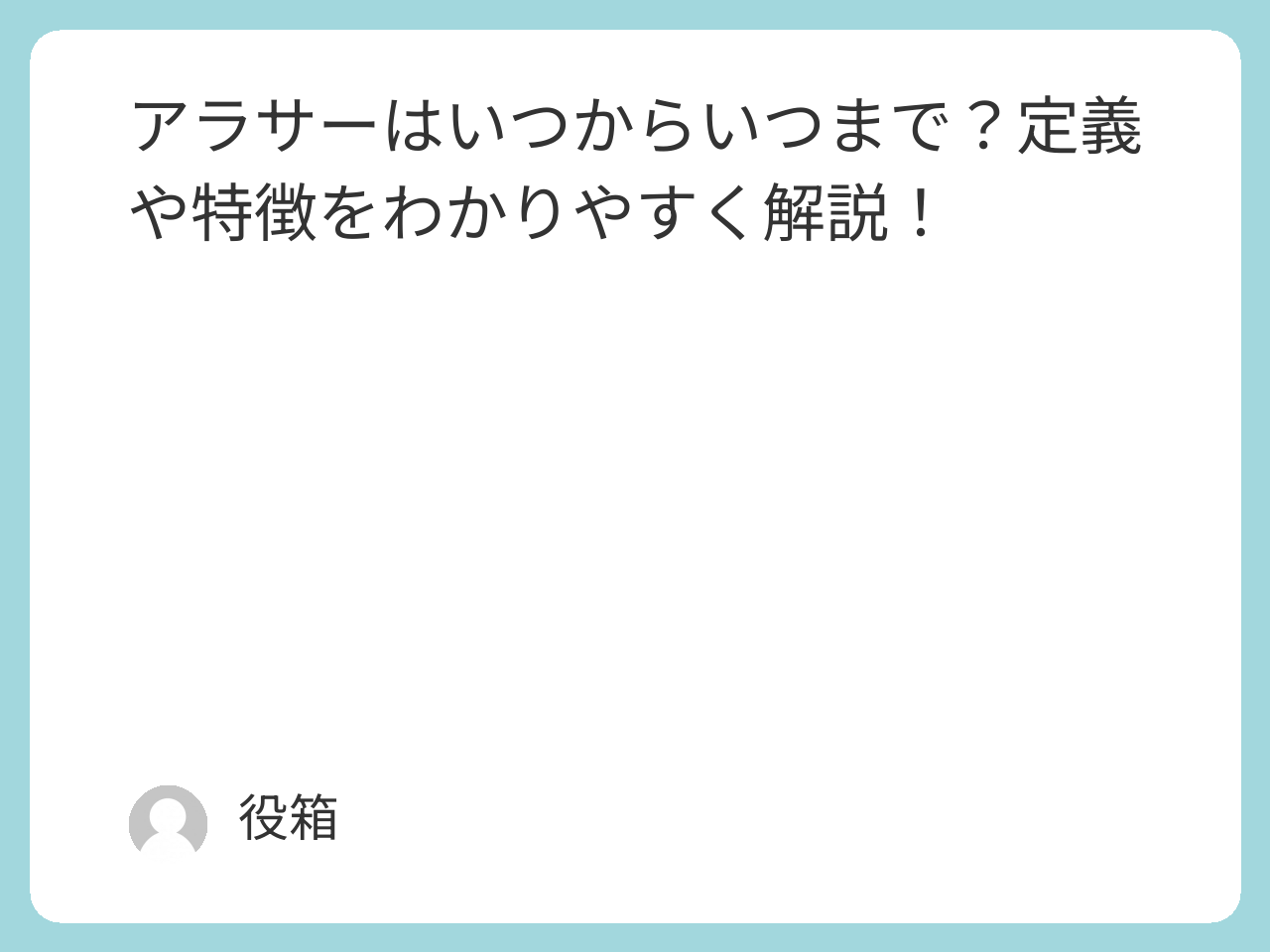一年の感謝の気持ちを込めて贈る「お歳暮」は、日本の伝統的な習慣のひとつです。
しかし、贈る時期やマナーには地域や相手との関係性によって微妙な違いがあり、
正しいタイミングや作法を知らないと失礼にあたることもあります。
お歳暮を贈る際には、どのような品物を選ぶべきか、
相手に失礼にならない金額の相場、のしの書き方など、
意外と気をつけるべきポイントが多く存在します。
本記事では、お歳暮を贈るのにふさわしい時期や基本的なマナーをわかりやすく解説します。
贈り物を通じて感謝の気持ちをしっかり伝えるために、ぜひ参考にしてください。
お歳暮の基本知識
お歳暮とは?その意味と目的
お歳暮とは、年末にお世話になった方々へ感謝の気持ちを込めて贈る贈り物のことです。日本の伝統的な習慣の一つであり、親族や上司、取引先などへの感謝を表す大切な行事です。
贈り物としてのお歳暮の役割
お歳暮は単なる贈り物ではなく、人間関係を円滑にする役割を持っています。年の瀬に感謝の気持ちを伝えることで、次の年も良好な関係を築くきっかけになります。
お歳暮とお中元の違い
お中元は夏の贈り物であり、健康や無事を願う意味合いが強いのに対し、お歳暮は一年の感謝を伝えるための贈り物です。
お歳暮を贈る時期はいつからいつまで?
お歳暮を贈る時期は、一般的に12月初旬から12月20日頃までとされています。しかし、地域や習慣によって多少の違いがあり、贈る相手によっても適切な時期が異なります。特に企業関係の取引先に送る場合は、年末の業務が忙しくなる前に届くように調整することが大切です。
また、最近ではオンラインショッピングの普及により、お歳暮の予約注文や早期発送が可能になり、11月下旬から贈る人も増えているのが特徴です。ただし、あまり早すぎると「お歳暮」として認識されず、季節感がずれる可能性があるため注意が必要です。
地域ごとのお歳暮の贈る時期
お歳暮を贈る時期は全国で統一されているわけではなく、地域ごとに慣習が異なります。特に関東と関西では贈る時期に違いがあるため、相手の住んでいる地域の習慣を考慮することが大切です。
主要地域別のお歳暮の贈る時期
-
関東地方(東京・神奈川・千葉・埼玉など)
12月1日~12月20日頃が一般的。関東では比較的早い時期から贈る習慣があります。 -
関西地方(大阪・京都・兵庫など)
12月10日~12月20日頃が目安。関東より少し遅めに贈るのが一般的です。 -
北海道・東北・中部・中国・四国・九州地方
12月初旬~12月20日頃までに贈るのが一般的。ただし、地域によっては12月15日以降に贈る習慣のところもあります。 -
沖縄地方
明確な決まりはないものの、12月中旬までに贈ることが多いです。
関東と関西で贈る時期が異なるのは、お中元の時期の違いと同じ理由で、江戸時代からの風習の違いが影響していると言われています。
企業や個人へのお歳暮の贈るタイミング
お歳暮を贈る相手によって、贈る時期を考慮する必要があります。特に、企業や取引先に贈る場合と、個人(家族や友人)に贈る場合では、適切なタイミングが異なります。
企業・取引先へのお歳暮
- 会社や役職者宛にお歳暮を贈る場合、12月10日~15日頃までに贈るのが理想的です。
- 企業では年末年始の休業があるため、12月20日以降に贈るのは避けたほうがよいでしょう。
- 取引先が忙しい時期に届いてしまうと、十分な対応ができない可能性があるため、なるべく早めに贈るのが望ましいです。
- 企業によっては「お歳暮の受け取りを禁止している場合」もあるので、事前に確認するのがベストです。
個人(親戚・友人・恩師など)へのお歳暮
- 12月初旬から12月20日頃までに贈るのが一般的です。
- 遅くともクリスマス前までに届くようにすると、年末の忙しい時期と重ならず、相手が落ち着いて受け取れます。
- 家族や親族などの親しい間柄では、多少時期が前後しても大きな問題はありませんが、できるだけ12月20日までには贈るとよいでしょう。
お歳暮の贈る時期に関する注意点
お歳暮を贈る際には、時期に関するマナーや配慮が必要です。以下のポイントを押さえて、相手に失礼のないようにしましょう。
1. 年内に贈るのが基本
お歳暮は「年内に感謝の気持ちを伝えるための贈り物」であるため、12月20日頃までには届くようにするのが一般的です。
ただし、配送が混雑する年末ギリギリは避け、早めに準備するのが望ましいです。
2. 遅れた場合の対応
もし12月20日を過ぎてしまった場合は、無理に「お歳暮」として贈るのではなく、**「寒中見舞い」**として贈るのがマナーです。
寒中見舞いは、1月7日(松の内が明けた後)から2月3日(節分)までの間に贈るのが一般的です。
3. のし紙の選び方
お歳暮に適したのし紙は、「紅白の蝶結び」のものを選び、表書きには「お歳暮」と書きます。
もし12月20日を過ぎて「寒中見舞い」として贈る場合は、「寒中御伺い」と表書きを変更しましょう。
4. 企業や取引先への贈答マナー
近年では、企業が**「贈答品の受け取りを禁止」**しているケースも増えています。
取引先や会社に贈る前に、事前に確認することが重要です。
お歳暮はいつから始まるのか?
一般的に、お歳暮の贈り始めは11月下旬から12月初旬とされています。ただし、企業や取引先へ贈る場合、年末の業務の都合上、12月初旬までに手配するのが望ましいとされています。また、百貨店やオンラインショップでは、11月初旬からお歳暮商品の予約販売が開始されることも多く、早めの準備が推奨されます。
お歳暮はいつまでに送りたい?
関東では12月初旬から12月20日頃まで、関西では12月10日から12月25日頃までに贈るのが一般的です。しかし、企業によっては年末が近づくと受け取りが難しくなるため、可能な限り早めに手配すると良いでしょう。また、遅れてしまった場合は「寒中見舞い」として1月7日以降に贈るのも一つの方法です。
お歳暮を贈る最適なタイミングとは?
お歳暮を贈る最適なタイミングは、12月初旬から12月20日頃までとされています。お歳暮は一年の感謝を伝える贈り物であり、適切な時期に贈ることで、より相手に好印象を与えることができます。関東と関西では慣習が異なり、関東は12月1日から、関西は12月10日頃から贈るのが一般的です。
ただし、最近ではインターネット通販の普及により、11月下旬からお歳暮の配送が始まるケースも増えているため、早めに贈る人も多くなっています。しかし、時期が早すぎると「お歳暮」としての認識が薄れる可能性があるため、適切なタイミングを意識することが重要です。
| 贈る対象 | 最適なタイミング |
|---|---|
| 関東地方 | 12月1日~12月20日頃 |
| 関西地方 | 12月10日~12月20日頃 |
| 企業・取引先 | 12月10日~15日頃 |
| 親族・友人 | 12月初旬~12月20日頃 |
| 遅れた場合 | 1月7日~2月3日(寒中見舞いとして) |
地域ごとのお歳暮の贈る最適なタイミング
お歳暮を贈るタイミングは、地域によって違いがあります。関東と関西では慣習が異なり、他の地域もそれに準じる形でお歳暮を贈る期間が決まっています。
関東地方(東京・神奈川・千葉・埼玉など)
- 12月1日~12月20日頃
- お歳暮を早めに贈る傾向があり、12月初旬から準備するのが一般的
- 企業や取引先にもこの時期に贈ることが多い
関西地方(大阪・京都・兵庫など)
- 12月10日~12月20日頃
- 関東より少し遅れて贈る習慣がある
- 「師走」に入ってから準備する人が多く、12月10日頃が目安
北海道・東北・中部・中国・四国・九州地方
- 12月初旬~12月20日頃
- 地域によって多少の違いがあるものの、基本的には関東や関西の習慣に準じる
沖縄地方
- 12月中旬まで
- 年末のイベントやお正月の準備が早いため、比較的早めに贈るのが一般的
お歳暮は12月20日までに相手のもとに届くように準備するのが基本ですが、地域の習慣を考慮して、適切なタイミングで贈ることが重要です。
企業や取引先へのお歳暮の最適なタイミング
企業や取引先にお歳暮を贈る場合、通常より少し早めに贈ることが重要です。
特に12月下旬は業務が繁忙期に入るため、12月10日~15日頃までに届くように手配するのが理想的です。
企業へお歳暮を贈る際のポイント
- 12月20日を過ぎると、年末年始の休業に入る企業が多いため、避けるのがベスト
- 担当者が不在になる可能性もあるため、できるだけ早めに手配する
- 企業によっては「贈答品の受け取りを禁止」している場合があるので、事前確認が必要
- 訪問して手渡しする場合は、担当者のスケジュールを事前に調整する
企業宛のお歳暮は、相手の業務に負担をかけないよう配慮し、適切なタイミングで贈ることが求められます。
親族・友人へのお歳暮の最適なタイミング
親族や友人にお歳暮を贈る場合は、12月初旬から12月20日までに届くように手配するのが一般的です。
この時期を過ぎると、クリスマスや年末年始の準備で忙しくなり、受け取る側の負担になる可能性があります。
親族・友人へ贈る際のポイント
- 遠方の親戚には、早めに配送手配をするのが安心
- 直接持参する場合は、相手の都合を事前に確認する
- 子どもがいる家庭には、年末のイベントを考慮して贈ると喜ばれる
お歳暮は、相手が忙しくなる前に受け取れるようにすることで、より感謝の気持ちが伝わります。
遅れた場合の対応
お歳暮の贈る最適な時期を過ぎてしまった場合は、「寒中見舞い」として贈るのが一般的です。
寒中見舞いの贈るタイミング
- 1月7日~2月3日(節分)まで
- のし紙の表書きを「お歳暮」から「寒中御伺い」に変更する
- 本来のお歳暮の意味合いとは異なるが、感謝の気持ちを伝えることはできる
寒中見舞いとして贈る場合は、遅れたことを謝罪しつつ、「新年のご挨拶として」などの文言を添えると丁寧な印象になるでしょう。
早めに贈る場合の注意点
お歳暮は、11月下旬から受付が始まることも多いですが、あまりに早すぎると「お歳暮」としての意味が薄れてしまう可能性があります。
早めに贈る際のポイント
- 11月中は避け、12月に入ってから贈るのが理想的
- 相手の受け取り状況を考え、年末に近くなりすぎないよう注意する
- オンラインショップの早期割引などを活用するのも一つの方法
早めに贈る場合でも、お歳暮の本来の意味を考え、12月に入ってから手配するのが望ましいです。
地域別のお歳暮の特徴
お歳暮は、日本各地で古くから続く感謝の贈り物ですが、その贈る時期や習慣は地域によって異なります。関東と関西ではお歳暮を贈るタイミングが違い、さらに北海道や九州などの地方によっても独自の風習があります。また、贈る品物の選び方にも地域性が表れ、地元の特産品を贈る文化が根付いている地域も少なくありません。相手の住んでいる地域の慣習を理解し、適切な時期と品物を選ぶことで、より心のこもったお歳暮を贈ることができます。
関東地方のお歳暮の習慣
関東では、12月初旬から12月20日頃までに贈るのが一般的です。特に東京都内では、取引先や上司などへの贈り物としてお歳暮を贈る習慣が根強く、デパートや百貨店ではお歳暮シーズンに多くの特設コーナーが設置されます。また、都心部では早めの手配が必要とされるため、11月中に準備を始める人も多いです。さらに、関東地方ではハムや高級お菓子などの詰め合わせが人気であり、実用性のある食品ギフトが好まれる傾向にあります。
関西地方のお歳暮の特徴
関西では、お歳暮の時期がやや遅く、12月10日から25日頃までに贈る習慣があります。京都や大阪では、格式を重んじる文化があるため、お歳暮の品物選びにもこだわる傾向があります。特に高級和菓子や特産品が人気で、相手の好みに応じた贈り物を選ぶことが重要とされています。さらに、関西では親しい間柄でもお歳暮を贈ることが多く、家庭同士でのやり取りが一般的です。加えて、贈る品には歴史や伝統を意識したものが選ばれることが多く、例えば関西の地元の銘品や職人が作る逸品が好まれます。
沖縄や九州の独自の文化
沖縄や九州では、お歳暮を贈る文化が関東・関西ほど根付いていないものの、親しい人や取引先に贈る風習があります。特に九州地方では、地元の特産品をお歳暮として贈ることが多く、例えば福岡の明太子や長崎のカステラなどが人気の品物です。沖縄では、泡盛や特産のフルーツギフトが贈られることが一般的であり、地域独自の文化を反映したお歳暮が多く見られます。また、九州・沖縄では、お歳暮を贈る相手との関係性を重視し、フォーマルなものよりも気軽な贈り物として扱われることが特徴です。加えて、沖縄では伝統的な工芸品や地元の加工食品が選ばれることもあり、贈り物を通じて地域文化を伝える役割も担っています。
お歳暮のマナーと注意点
お歳暮を贈る際には、相手に失礼のないよう、基本的なマナーを守ることが大切です。
贈る時期、のし紙の選び方、品物の選定、喪中の相手への配慮など、正しい方法を知っておくことで、より気持ちのこもった贈り物になります。
ここでは、お歳暮の基本マナーと注意点について詳しく解説します。
1. お歳暮を贈る時期のマナー
お歳暮を贈る最適な時期は、12月初旬から12月20日頃までとされています。
しかし、地域や相手の状況によっては、多少の違いがあるため注意が必要です。
関東と関西で異なるお歳暮の贈る時期
-
関東地方(東京・神奈川・千葉・埼玉など)
12月1日~12月20日頃に贈るのが一般的。比較的早めにお歳暮を贈る習慣があります。 -
関西地方(大阪・京都・兵庫など)
12月10日~12月20日頃に贈るのが一般的。関東よりやや遅めの時期に贈る風習があります。 -
その他の地域(北海道・東北・中部・中国・四国・九州など)
12月初旬~12月20日頃が目安。地域によって若干異なる場合があります。
遅れた場合の対応
12月20日を過ぎてしまった場合は、無理に「お歳暮」として贈るのではなく、
「寒中見舞い」として1月7日~2月3日(節分)までに贈るのがマナーです。
2. のし紙の正しい使い方
お歳暮を贈る際には、「のし紙」をつけるのが一般的なマナーです。
のし紙には「水引」と「表書き」があり、適切なものを選ぶ必要があります。
のし紙の選び方
-
水引の種類:「紅白の蝶結び」
(何度でも結び直せるため、お祝い事や日常の贈り物向き) -
表書き:「お歳暮」と記載
(遅れて贈る場合は「寒中御伺い」などに変更) -
個人宛と会社宛の違い
- 個人に贈る場合は、**表書きを「お歳暮」**とするのが一般的。
- 会社宛に贈る場合は、会社名を入れたのし紙を使用するとより丁寧です。
3. お歳暮の品物の選び方とマナー
お歳暮は相手が喜ぶ品物を選ぶことが大切です。ただし、贈る相手によっては、避けるべき品物もあります。
お歳暮の品物の選び方
-
定番の人気商品
- お菓子(和菓子・洋菓子)
- 果物(高級フルーツ)
- コーヒー・紅茶・お茶
- 酒類(ワイン・日本酒・焼酎)
- 高級食材(カニ・肉・海産物)
-
避けるべき品物
- 櫛(苦・死を連想させる)
- 刃物(縁を切る意味を持つ)
- 白いハンカチ(死を連想させる)
- 高価すぎる贈り物(相手に気を遣わせる)
お歳暮の相場
- 親族・友人宛:3,000円~5,000円
- 取引先・上司宛:5,000円~10,000円
4. 企業や取引先へのお歳暮のマナー
企業や取引先にお歳暮を贈る際には、事前に会社のルールを確認することが重要です。
最近では、「贈答品の受け取りを禁止」している企業もあるため、いきなり贈らずに確認するのがマナーです。
企業宛にお歳暮を贈る際のポイント
-
贈る相手の役職や立場を考慮する
- 直属の上司や社長宛に贈る場合、個人名ではなく、部署名や会社名を記載するのが一般的。
-
贈るタイミングを考慮する
- 企業は12月下旬から年末年始の休業に入るため、12月10日~15日頃に贈るのが理想的。
5. 喪中の場合の贈り方と配慮
お歳暮は「お祝い」ではなく「感謝の気持ちを伝える贈り物」なので、基本的には喪中でも贈ることが可能です。
ただし、喪中の方に配慮しながら贈ることが大切です。
喪中の相手にお歳暮を贈る際の注意点
-
忌中(四十九日)が明けてから贈る
- 四十九日より前に贈るのは避けるのがマナー。
-
のし紙を使わない
- 紅白の水引を避け、無地の掛け紙を使用する。
- 表書きを「御伺い」や「寒中御伺い」にすると、より配慮が伝わる。
-
相手に確認してから贈るのも選択肢
- 「喪中のため、お歳暮を控えます」と伝えた上で、相手の意向を確認するのも一つの方法。