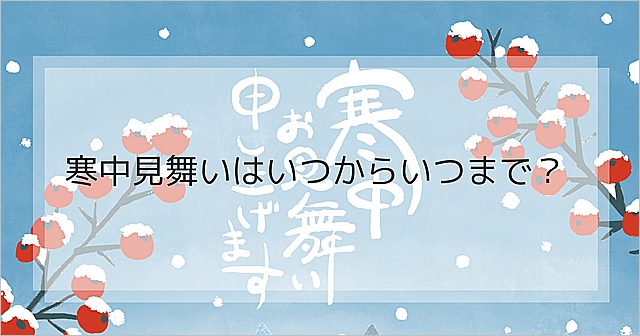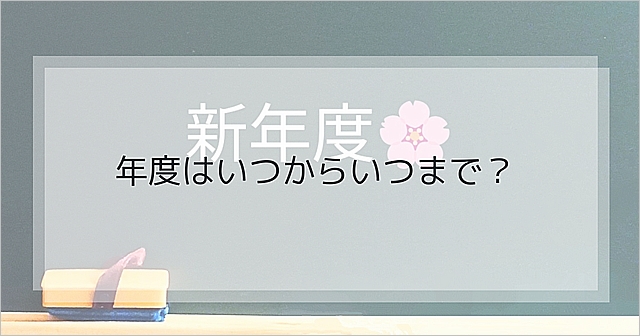寒さが厳しくなる季節に、
相手を気遣う気持ちを込めて送る「寒中見舞い」。
年賀状を出しそびれたときや、
喪中の方への挨拶として用いられることが多いですが、
正しい時期やマナーを意識して送ることが大切です。
送る時期を間違えると、相手に失礼にあたることもあるため、
適切なタイミングを知っておくことが重要になります。
また、寒中見舞いの書き方や、
どのような文面がふさわしいのかも気になるところです。
特にビジネスシーンや目上の方への挨拶では、
丁寧な表現を心がける必要があります。
この記事では、寒中見舞いを送る
正しい期間やマナーについて詳しく解説します。
適切なタイミングで気持ちを伝えられるよう、
ぜひ最後までご覧ください。
寒中見舞いはいつからいつまで?
寒中見舞いを送る期間は、松の内が終わった後から立春の前日までが一般的です。
松の内とは、お正月飾りを飾っている期間のことで、地域によって違いがあります。
関東では1月7日、関西では1月15日までとされており、
寒中見舞いはその翌日から送るのが基本です。
また、寒中見舞いの終わりの時期は立春の前日です。
立春は毎年2月4日ごろにあたるため、寒中見舞いを送る適切な期間は、
関東なら1月8日から2月3日まで、
関西なら1月16日から2月3日までということになります。
年賀状の代わりに送る場合や、喪中の方への挨拶として送る場合でも、この期間を守ることが大切です。時期を過ぎると「余寒見舞い」として扱われることになるため、送る際には注意しましょう。
寒中見舞いを送る時期の詳細
松の内が明けた後に送る
寒中見舞いは、松の内が終わってから送るのが基本です。松の内の期間は、関東と関西で異なります。
- 関東の松の内:1月1日~1月7日
- 関西の松の内:1月1日~1月15日
松の内とは、門松やしめ縄などのお正月飾りを飾っておく期間のことです。地域によって異なりますが、松の内が終わると、お正月ムードが落ち着くため、それ以降に寒中見舞いを送るのがマナーとされています。
立春の前日までが寒中見舞いの期間
寒中見舞いは、冬の寒さが厳しい時期に送る挨拶状です。そのため、「寒の内」と呼ばれる期間内に送るのが望ましいとされています。「寒の内」は、二十四節気の「小寒」(1月5日ごろ)から「立春」(2月4日ごろ)の前日までの期間を指します。
したがって、寒中見舞いを送ることができるのは1月8日(または1月16日)から2月3日までです。立春を過ぎると「余寒見舞い」となるため、送るタイミングには気をつけましょう。
寒中見舞いを送る適切なタイミング
寒中見舞いを送るタイミングは、状況によって変わります。以下のようなケースでは、特に時期に気をつけて送りましょう。
① 喪中の方への挨拶として送る場合
喪中の方へ年賀状を送ることは避けるのがマナーですが、その代わりとして寒中見舞いを送ることができます。喪中はがきを受け取った場合、年賀状は控え、松の内が明けた後に寒中見舞いを送るのが適切です。
- 関東の場合:1月8日以降
- 関西の場合:1月16日以降
年賀状のような華やかなデザインではなく、落ち着いた色合いのはがきを選び、丁寧な言葉を使うことが大切です。
② 年賀状を出しそびれた場合
年賀状のやり取りをするつもりだったのに、年始の忙しさで出し忘れてしまった場合、寒中見舞いとして送るのが一般的です。この場合も、松の内が明けた後に送りましょう。
ただし、年賀状の代わりに送るとはいえ、「新年おめでとうございます」といったお祝いの言葉は避けるようにします。「寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか」といった挨拶から始めるとよいでしょう。
③ 寒中見舞いを送る時期を過ぎた場合
もし寒中見舞いを送る時期を過ぎてしまった場合は、「余寒見舞い」として送ることができます。寒の内を過ぎた2月4日以降に送る場合、「寒中見舞い」ではなく「余寒見舞い」と書くのが適切です。
寒中見舞いの適切な送付期間まとめ
| 送付目的 | 送付開始時期 | 送付終了時期 |
|---|---|---|
| 一般的な寒中見舞い | 1月8日(関東)、1月16日(関西) | 2月3日 |
| 喪中の方への挨拶 | 1月8日(関東)、1月16日(関西) | 2月3日 |
| 年賀状を出しそびれた場合 | 1月8日(関東)、1月16日(関西) | 2月3日 |
| 余寒見舞い | 2月4日 | 2月末頃まで |
寒中見舞いは、季節の挨拶として大切な習慣です。適切なタイミングで送ることで、相手に失礼のない気遣いを伝えることができます。送る際には、時期だけでなく、文面やデザインにも注意し、心のこもった挨拶状を送りましょう。
寒中見舞いとは?意味や役割を知ろう
寒中見舞いとは、冬の寒さが厳しい時期に相手を気遣うために送る挨拶状です。年賀状を出しそびれた場合や、喪中の方への配慮として用いられることもあります。
また、寒中見舞いは、お正月の松の内が明けた後(関東では1月8日、関西では1月16日)から立春の前日(2月3日)までに送るのが一般的です。
寒中見舞いは、もともと冬の厳しい気候の中で相手の健康を気遣うための習慣でした。しかし、時代とともに年賀状の代わりや、喪中の方への挨拶としての役割も持つようになり、現在では幅広い目的で利用されています。
寒中見舞いの役割
寒中見舞いには、主に4つの役割があります。
それぞれのシーンに応じた適切な表現を選ぶことで、相手に対する心遣いが伝わりやすくなります。
① 相手の健康や生活を気遣う
寒中見舞いは、冬の寒さが厳しくなる時期に相手の健康を気遣う目的で送るものです。特に遠方に住んでいる家族や親族、しばらく会っていない友人に送ることで、近況を伝えながら「寒さに負けず元気に過ごしてください」といったメッセージを届けることができます。
文面には、以下のようなフレーズがよく使われます。
- 「寒さが厳しいですが、お変わりありませんか?」
- 「寒い日が続きますので、お体を大切になさってください」
受け取った相手が温かい気持ちになれるよう、丁寧な言葉を選びましょう。
② 喪中の方への挨拶
喪中の方に年賀状を送るのはマナー違反とされていますが、その代わりに寒中見舞いを送ることで、新年の挨拶を控えつつ、相手への気遣いを伝えることができます。
喪中の方への寒中見舞いでは、お祝いの言葉や華やかなデザインを避け、落ち着いた表現を心がけることが大切です。以下のような文面が適しています。
- 「寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください」
- 「喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきましたが、本年もよろしくお願い申し上げます」
また、相手の心情に配慮し、あまり長い文章にせず、簡潔にまとめるのがよいでしょう。
③ 年賀状の代わりとして送る
年賀状を出しそびれてしまった場合、寒中見舞いとして挨拶をすることができます。この場合も、お祝いの言葉は避け、年賀状よりも控えめな表現を使うのがマナーです。
年賀状の代わりに送る寒中見舞いでは、以下のような文面が一般的です。
- 「年始のご挨拶が遅くなりましたことをお詫び申し上げます」
- 「寒さが続きますが、どうかお健やかにお過ごしください」
年賀状を出しそびれたことに対するお詫びの言葉を添えつつ、相手を気遣う一言を加えると、丁寧な印象になります。
④ 年賀状の返信として送る
喪中のために年賀状を控えていた場合でも、相手から年賀状が届いた場合は、その返信として寒中見舞いを送ることができます。
この場合、「喪中につき年始のご挨拶を失礼しました」と一言添えると、相手への配慮が伝わります。文面の例としては、以下のような表現が適しています。
- 「ご丁寧な年賀状をありがとうございました。喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきましたが、本年もよろしくお願い申し上げます」
- 「寒中お見舞い申し上げます。寒さが続きますが、お身体にお気をつけてお過ごしください」
このように、感謝の気持ちを伝えながらも、お祝いの雰囲気を避けることがポイントです。
寒中見舞いの基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 相手の健康を気遣う、年賀状の代用、喪中の方への配慮 |
| 送付時期 | 松の内が明けた後(関東:1月8日~、関西:1月16日~)から立春の前日(2月3日)まで |
| 送る相手 | 親族、友人、取引先、喪中の方 |
| 文面のポイント | お祝いの言葉は避け、寒さを気遣う表現を用いる |
| 代表的な文例 | 「寒さ厳しき折、ご自愛ください」「寒い日が続きますが、どうかお元気で」 |
寒中見舞いの正しい書き方とマナー
寒中見舞いを書く際は、季節の挨拶や相手を気遣う言葉を適切に表現することが大切です。
また、年賀状の代わりや喪中の方への配慮として送る場合、それぞれに適した文面があります。
寒中見舞いは、決まったルールを守りつつ、心のこもったメッセージを伝えることが重要です。
寒中見舞いの基本構成
寒中見舞いの文章には、一定の型があり、主に5つのパートで構成されます。
- 季節の挨拶(寒中お見舞い申し上げます)
- 相手の健康や生活を気遣う言葉
- 寒中見舞いを送る理由(喪中のため、年賀状の代わりなど)
- 自分の近況報告(簡潔に)
- 結びの挨拶(相手の健康を願う言葉)
この流れに沿って書くことで、形式に沿った美しい寒中見舞いになります。
寒中見舞いの書き方のポイント
① 書き出しの挨拶
寒中見舞いは、時候の挨拶から始めます。
一般的には「寒中お見舞い申し上げます」と書きますが、丁寧な表現として**「寒中お伺い申し上げます」**もあります。
また、親しい間柄であれば、もう少し柔らかい表現を使うことも可能です。
書き出しの例
- 「寒中お見舞い申し上げます。」
- 「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「厳寒の候、皆様のご健康をお祈り申し上げます。」
② 相手の健康を気遣う一言
寒い季節に送るため、相手の健康を気遣う言葉を添えるのが基本です。
これは、寒中見舞いの本来の目的である「相手への気遣い」を表現する大切な部分です。
健康を気遣う例
- 「厳しい寒さが続きますが、お変わりありませんか。」
- 「風邪などひかれませんよう、ご自愛ください。」
- 「春の訪れまで、どうぞお身体を大切になさってください。」
③ 寒中見舞いを送る理由
寒中見舞いを送る理由は、相手との関係や状況によって異なります。
目的に応じて、適切な表現を選びましょう。
(1)喪中のため年賀状を控えた場合
喪中の方に対して、新年のお祝いを避けつつも、季節の挨拶を送る目的で使用します。
この場合、慎ましい表現を心がけることが大切です。
文例
- 「昨年○○を亡くし、喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきました。」
- 「寒さ厳しき折、どうかご自愛くださいますようお祈り申し上げます。」
(2)年賀状の返信を兼ねる場合
年賀状を受け取ったが、自分は年賀状を出さなかった場合、寒中見舞いとして返信します。
文例
- 「ご丁寧な年賀状をいただき、ありがとうございました。」
- 「寒中にて恐縮ですが、改めまして本年もよろしくお願いいたします。」
(3)年賀状を出しそびれた場合
年賀状の代わりに寒中見舞いを送る場合は、お詫びの言葉を添えながら、今後の関係を大切にする一言を加えると良いでしょう。
文例
- 「新年のご挨拶が遅くなり、申し訳ございません。」
- 「寒さ厳しき折ですが、どうかお健やかにお過ごしください。」
④ 結びの挨拶
最後は、相手の健康や幸福を願う言葉で締めくくります。
ビジネスシーンではフォーマルな表現を、親しい間柄では少し柔らかい表現を使い分けるとよいでしょう。
結びの例
- 「寒さ厳しき折、ご自愛のほどお願い申し上げます。」
- 「厳寒の折、どうぞお体を大切になさってください。」
- 「お互いに元気に春を迎えられますよう、お祈り申し上げます。」
寒中見舞いのマナー
① 送る時期に注意する
寒中見舞いは、「寒の内」に送るのが基本です。
松の内(1月7日または1月15日)が明けた後、1月8日~2月3日までに送るのが適切です。
これを過ぎると「余寒見舞い」となるため、文面を変更する必要があります。
② お祝いの言葉は避ける
寒中見舞いでは、「新年おめでとうございます」「賀正」などのお祝いの言葉は避けましょう。
特に喪中の方に送る場合は、慎ましい表現を使うことが重要です。
③ 使うはがきの種類
寒中見舞いは年賀状とは異なり、通常の郵便はがきを使用します。
喪中の方に送る場合は、白無地や落ち着いたデザインのはがきを選ぶのがマナーです。
④ 送り先に合わせた文面にする
友人や家族に送る場合は、少しカジュアルな表現でも問題ありませんが、
ビジネス関係の相手や目上の方に送る場合は、敬語を使い、より丁寧な表現を心がけましょう。
寒中見舞いの書き方とマナーのまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書き出し | 「寒中お見舞い申し上げます」などの時候の挨拶から始める |
| 健康を気遣う言葉 | 「寒さ厳しき折、お変わりありませんか」など相手を気遣う一言を添える |
| 寒中見舞いを送る理由 | 喪中のため、年賀状の代わり、返信の挨拶など、状況に応じた内容を書く |
| 結びの言葉 | 「くれぐれもお身体を大切になさってください」など、相手の健康を願う言葉で締めくくる |
| 送る時期 | 1月8日~2月3日(松の内明け~立春の前日) |
| NG表現 | 「新年おめでとう」「賀正」などのお祝いの言葉は避ける |
| はがきの種類 | 年賀はがきではなく、通常の郵便はがきを使用する |
寒中見舞いの書き方 例文
ビジネス向けの寒中見舞いの書き方は?
ビジネスシーンでは、よりフォーマルな表現を用いることが求められます。
寒中お見舞い申し上げます。
寒さが厳しい折、貴社の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和○年○月○日
喪中の方への寒中見舞いはどう書く?
喪中の方には「新年の祝い言葉」を避けることがマナーです。
寒中お見舞い申し上げます。
ご服喪中とのこと、心よりお悔やみ申し上げます。
寒さ厳しき折、くれぐれもお身体を大切にお過ごしください。
令和○年○月○日
寒中見舞いの由来と歴史
寒中見舞いの由来は、日本の古くからの「季節の挨拶」の文化に根付いています。
もともと、冬の厳しい寒さの中で相手の健康を気遣い、直接訪問して言葉を交わす風習がありました。
この風習が、時代の流れとともに手紙やはがきの形へと変化し、現在の寒中見舞いとして定着しました。
また、寒中見舞いの背景には、「寒の内(かんのうち)」という暦の考え方が関わっています。
寒の内とは、二十四節気の「小寒」(1月5日ごろ)から「立春」(2月4日ごろ)の前日までの期間を指し、
一年の中で最も寒さが厳しい時期とされています。
この時期に、遠方の家族や知人の健康を気遣うために手紙を送る習慣が生まれ、
それが「寒中見舞い」として定着したと考えられています。
寒中見舞いの歴史
寒中見舞いの歴史は、江戸時代にまでさかのぼります。
当時は、武士や商人の間で新年の挨拶として「年賀回り」をするのが一般的でした。
しかし、遠方に住んでいる相手には直接訪問することが難しく、手紙で新年の挨拶を送る風習が生まれました。
これが、年賀状の原型とされています。
その後、喪中の人が新年の挨拶を控えるようになり、松の内が明けた後に代わりの挨拶状を送る習慣が広がりました。
これが、現在の寒中見舞いの起源とされています。
明治時代に入ると、郵便制度が整備され、手紙のやり取りがより身近なものになりました。
その結果、寒中見舞いも一般の人々に広まり、現在のように「年賀状を出しそびれた際の代用」や
「喪中の際の挨拶」として使われるようになりました。
また、昭和時代になると印刷技術が向上し、寒中見舞い専用のはがきも販売されるようになりました。
これにより、寒中見舞いを送る習慣がより一般化し、ビジネスシーンでも用いられるようになりました。
寒中見舞いの変遷
寒中見舞いの形は時代とともに変化してきました。
それぞれの時代ごとに、寒中見舞いの使われ方や役割が少しずつ変わってきています。
① 江戸時代
- 新年の挨拶として、武士や商人が書状を送る習慣があった。
- 喪中の人が年賀状を控える代わりに、松の内が明けた後に挨拶状を送るようになった。
- 遠方の親戚や知人に対して、直接会いに行けない場合の挨拶手段として利用された。
② 明治時代
- 郵便制度の確立により、手紙のやり取りが一般庶民にも広がった。
- 年賀状の文化が定着し、寒中見舞いは「年賀状を送れなかった場合の代用」として使われることが増えた。
- 商業的な年賀状の流通が活発化し、寒中見舞いもビジネスシーンで利用されるようになった。
③ 昭和~平成
- 印刷技術が発展し、寒中見舞い専用のはがきが販売されるようになった。
- 喪中の方への挨拶としての役割がより強まり、デザインも落ち着いたものが増えた。
- ビジネス用途でも使われるようになり、会社間の挨拶状としても普及した。
④ 現代
- SNSやメールの普及により、デジタルで寒中見舞いを送る人が増えた。
- 一方で、年配の方を中心に手書きのはがきを送る文化も残っている。
- カジュアルな寒中見舞いが増え、個人間のコミュニケーション手段としても活用されている。
寒中見舞いの由来と歴史のまとめ
| 時代 | 寒中見舞いの特徴 |
|---|---|
| 江戸時代 | 武士や商人が年始の挨拶として手紙を送る習慣があった。喪中の際は寒中見舞いが使われた。 |
| 明治時代 | 郵便制度の発展により、一般の人々にも手紙のやり取りが広がった。寒中見舞いの文化が定着。 |
| 昭和~平成 | 印刷技術の発展で、寒中見舞い用のはがきが販売されるようになり、喪中の方への挨拶として利用されることが増えた。 |
| 現代 | SNSやメールの普及によりデジタルで送る人も増加。一方で手書きの文化も根強く残る。 |
寒中見舞いは、日本の伝統的な文化の一つとして、長い歴史を持っています。
現代では、はがきだけでなく、メールやSNSを活用した新しい形の寒中見舞いも増えていますが、
根底にある「相手を気遣う心」は、時代が変わっても変わらず受け継がれています。
年賀状との違いは?
寒中見舞いと年賀状の違いは、主に送る時期と目的にあります。年賀状は元旦から松の内(1月7日頃)までに送るのが一般的ですが、寒中見舞いは松の内が明けた後に送ります。また、年賀状は新年の祝賀を目的としますが、寒中見舞いは相手を気遣う目的が強く、特に喪中の方に送ることができます。
寒中見舞いはいつからいつまで送れる?適切な時期とは
いつから送れる?(寒中見舞いの開始時期)
寒中見舞いは一般的に「松の内が明ける1月8日頃」から送るのが適切とされています。松の内とは、正月飾りを飾る期間のことで、地域によって異なりますが、関東では1月7日、関西では1月15日までが一般的です。よって、関東では1月8日、関西では1月16日から寒中見舞いを送ると良いでしょう。
いつまでに送ればいい?(寒中見舞いの終了時期)
寒中見舞いは「立春(2月3日または4日)」までに送るのが一般的です。立春を過ぎると、「余寒見舞い」となり、表現や文面が少し変わります。例えば、「寒さが続いておりますが、お体を大切にお過ごしください」という表現を使うと良いでしょう。
立春を過ぎたらどうすればいい?
もし寒中見舞いを出しそびれてしまった場合、2月4日以降は「余寒見舞い」として送ることができます。余寒見舞いは、まだ寒さが残る時期に相手の健康を気遣う挨拶状です。文面の内容は寒中見舞いと似ていますが、「寒さが和らぐまでご自愛ください」といった表現を加えると適切です。