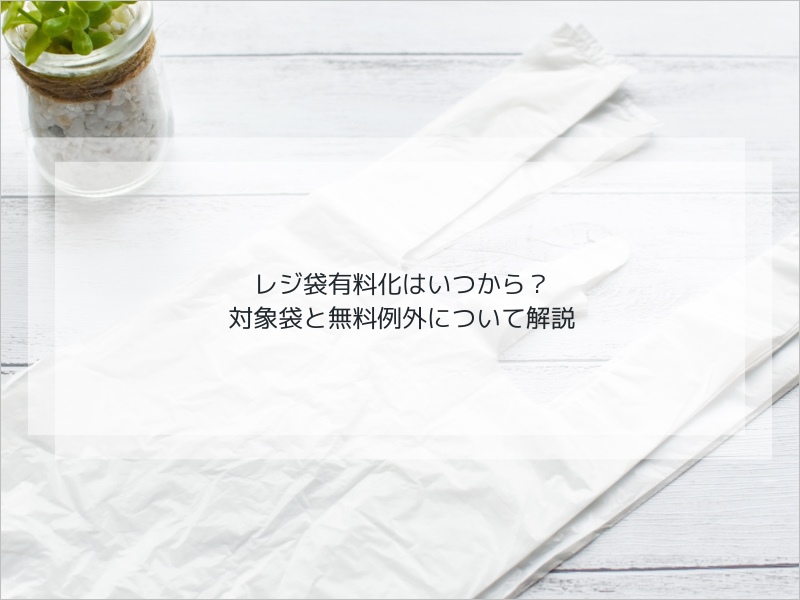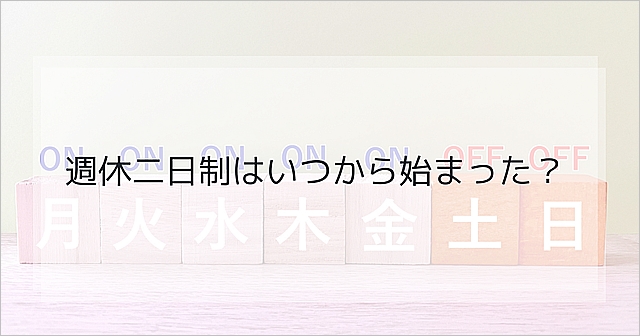日常の買い物で使われてきた袋が、
あるタイミングを境に料金がかかるようになった背景には、
環境や制度に関する明確なルールが存在します。
どんな袋が該当し、どれが対象外なのか、
その違いを知らずにレジで戸惑った経験がある方も少なくないはずです。
知らないうちに始まっていた制度や、
その中で例外とされるケースについて、
正しい情報を知ることは日々の買物に安心感をもたらしてくれます。
制度の概要とあわせて、わかりやすくご紹介していきます。
【結論】レジ袋の有料化はいつから始まった?全国での実施日は2020年7月1日【令和2年施行】
レジ袋の有料化はいつから始まったのでしょうか?
結論です。
令和2年7月1日からです。
日本全国でプラスチック製の
持ち手付きの買物袋が有料となり、
無料配布が原則禁止となりました。
この制度スタートは、環境問題や
プラスチックごみの削減をめぐる
背景が根底にあり、
地球温暖化や海洋汚染への対応として
政府が全国一律で導入を決定しています。
対象となるのは、持ち手のある
プラスチック製レジ袋で、
紙袋や布やバイオマス配合の
環境配慮型素材(一定以上の配合)などは
対象外ですし、
すでに厚さが50ミクロンを超えるような
再利用できる袋も除外されています。
このような区分けの仕組みは、
制度の趣意であるプラスチック
過剰使用の抑制と廃棄量の低減、
さらに私たち消費者の意識や
買物行動の変化を促すための、
有効な設計だといえるでしょう。
制度運用は義務化されており、
どの小売店でも対応が求められ、
販売価格は店舗が自由に決定できます。
ただし、1枚あたり1円未満の
価格設定は「有料化」とみなされず、
制度の意味を担保するための
基準も用意されています。
この制度導入後、エコバッグや
マイバッグを持参する消費者が
増えたのも象徴的です。
実際、レジ袋の使用量や廃棄量は
有料化により大きく減り、
全国的なプラスチック削減の
一翼を担っているのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 令和2年7月1日(2020年7月1日)から全国一律で実施 |
| 対象袋 | 持ち手付きプラスチック製の買物袋。紙袋・布袋・バイオマス配合や厚手袋は対象外。 |
| 目的・背景 | プラスチックごみ削減、海洋汚染・地球温暖化対策、消費者の意識変革を促す狙い。 |
| 制度の性質 | 全国一律・義務化。価格設定は店舗に委ねられるが、1円未満は「有料」と認められない基準あり。 |
| 消費者変化 | マイバッグ・エコバッグの利用増、使い捨てレジ袋の使用量・廃棄量の明確な抑制が実現。 |
有料化の対象となるレジ袋とは?プラスチック製袋と無料配布例外を解説
持ち手のあるプラスチック製レジ袋は、令和2年7月1日から全国で有料化され、対象として明確に位置づけられました。
これは、小売店やスーパーなどで商品購入時に提供される、
いわゆる「レジ袋」と呼ばれる袋のうち、一定の基準を満たすものに適用されます。
対象となる袋の具体例:
-
スーパーマーケットで商品を入れるために使うビニール製の袋
-
コンビニで会計後に渡される、取っ手付きのレジ袋
-
ドラッグストアや衣料品店など、買い物時に無料提供されていたビニール袋 など
これらの袋は、プラスチック素材でできており、
多くが一度きりの使い捨てを前提としていました。
そのため、環境への影響が大きく、
使い捨てプラスチックごみの排出量を減らすために有料化されることになりました。
また、この制度では「持ち手のあること」「プラスチック製であること」が有料化の重要な判断基準です。
厚さや素材によっては、同じ見た目の袋でも無料配布が認められる場合があります。
それについて、次で詳しく見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有料化の対象袋 | 持ち手付きのプラスチック製買い物袋(スーパー・コンビニ・小売店等) |
| 有料化の例外① | 厚さ50μm以上で「繰り返し使用可」表示あり |
| 有料化の例外② | 海洋生分解性プラスチック100%使用・表示がある袋 |
| 有料化の例外③ | バイオマス素材を25%以上配合・認証表示あり |
| その他の対象外の袋 | ・持ち手がない食品用小分け袋 ・包装用ショッパー ・薬袋や配送用袋など |
| 例外に必要な条件 | 明確な表示(再利用可・配合率・素材)や、用途による対象外の判断 |
有料化されない袋の条件とは?無料配布が認められる例外の種類
一律にすべてのレジ袋が有料になるわけではありません。
制度には、環境に配慮した袋や、用途が特殊な袋に対して例外を設けています。
以下の条件に当てはまる袋で、かつそれが明確に表示されている場合、無料での配布が可能です。
① 厚みがあるプラスチック袋(50μm以上)
袋の厚さが50マイクロメートル(μm)以上あり、
繰り返し使用できることを前提とした袋は、無料で提供できます。
これは「使い捨て」ではなく、「繰り返し利用による資源削減」が目的とされています。
店舗によっては、そうした袋に「繰り返し使えます」といった記載が印刷されています。
② 海洋生分解性プラスチック100%の袋
プラスチック素材の中でも、海水中で自然に分解される「海洋生分解性プラスチック」を100%使った袋も対象外です。
これらは、環境負荷が極めて低いため、有料化の対象から外されています。
ただし、必ず「100%海洋生分解性」と明記されていることが条件です。
③ バイオマス素材が25%以上配合された袋
バイオマス素材とは、とうもろこし・サトウキビ・じゃがいもなど、植物由来の原料でつくられたものです。
この素材が25%以上含まれている袋も、無料で配布できます。
「バイオマスマーク」や「配合率25%以上」などの表示が袋にあることが求められます。
これら3つのタイプは、「環境配慮型のプラスチック袋」として制度上優遇されており、
小売店側もこれらを選べば無料配布が可能となっています。
無料配布できるその他の袋とは?有料化の対象外となる特別なケース
制度では、素材や厚さ以外にも、「用途や状況」によって対象外となるケースがあります。
以下のような袋は、たとえプラスチック製であっても有料化の対象外です。
・持ち手がない袋(食品の小分け用など)
持ち手がないビニール袋は、制度の「持ち手付きレジ袋」の定義に該当しないため、対象外です。
たとえば、スーパーの野菜コーナーや精肉売場で使われている小分け袋は、無料のままです。
・商品の一部として提供される包装袋
衣料品店や土産物店などで、商品そのものの保護やデザイン性を重視して使われる袋(包装袋やショッパー)は、対象になりません。
また、プレゼント包装や景品を包む袋も、対象外とされています。
・消費者が辞退できない袋(薬袋や通信販売の同梱袋)
医療機関で処方された薬を入れる袋や、オンラインショップから届く配送袋など、
消費者が「袋をいらない」と断る選択肢がないものは、制度の適用外です。
こうした例外規定は、「消費者が判断・選択できる場面」に絞って制度を適用するために設けられたものです。
一律ではなく、目的や必要性に応じて柔軟に運用されているのがポイントです。
紙袋・布袋・バイオマス配合素材はレジ袋有料化の対象外?
紙袋や布袋、そしてバイオマス素材を一定割合含む袋は、
レジ袋有料化の制度において「対象外」とされています。
レジ袋有料化の対象となるのは、プラスチック素材でできた、
持ち手付きの買い物袋に限定されています。
そのため、紙を素材とする袋や布製の袋は、そもそも
プラスチック製ではないため、有料化の範囲から除かれます。
また、バイオマス配合素材の袋についても条件があります。
植物由来の素材が25%以上含まれている袋で、
それが明確に表示されている場合には、有料化の対象外です。
バイオマスとは、とうもろこしやさとうきびなど、
再生可能な資源から得られる原料のことを指します。
環境への影響を抑制する観点から、このような素材は
「環境配慮型の袋」として特別に扱われています。
一方、たとえバイオマス素材が使われていたとしても、
配合率が25%未満であったり、表示がなかったりする場合には
有料化の対象となりますので注意が必要です。
紙袋については、店舗によっては有料で提供しているところもありますが、
それは制度による義務ではなく、事業者の自由判断によるものです。
制度上は紙袋も布袋も「無料配布可」とされています。
このように、袋の素材や配合率、表示の有無が、
レジ袋有料化の対象かどうかを判断する基準になります。
消費者にとっては、素材を意識して袋を選ぶことが、
プラスチックごみ削減や資源の有効利用につながります。
マイバッグを持参することも含めて、私たち一人ひとりが
日々の買い物でできる取り組みのひとつといえるでしょう。
| 袋の種類 | レジ袋有料化の対象 | 理由と条件 |
|---|---|---|
| 紙袋 | 対象外 | プラスチック素材ではないため制度の対象外 |
| 布袋(トートバッグなど) | 対象外 | 繰り返し使用できる袋であり、有料化対象ではない |
| バイオマス配合袋(25%以上) | 対象外 | 植物由来素材が25%以上含まれており表示が必要 |
| バイオマス配合袋(25%未満) | 対象 | 配合率が基準に満たないため制度の対象 |
| プラスチック製レジ袋 | 対象 | 使い捨て・持ち手付きで制度の主な対象 |
レジ袋の有料化はなぜ始まった?背景・目的・環境問題との関係
レジ袋の有料化は、シンプルにいえば
プラスチックごみの削減を目指した政策として始まりました。
プラスチック製のレジ袋は、使い捨てされることが多く、
ごみとして大量に廃棄される傾向にあります。
日本では、1人あたりのプラスチックごみの排出量が多く、
地球規模での環境問題と無関係ではありません。
とくに、海洋へのプラスチックごみ流出や
海洋汚染は、生態系に深刻な影響を及ぼすため、
世界全体でも喫緊の対策が求められており、
日本も例外ではありませんでした。
そこで、政府は令和2年(2020年)7月1日から、
小売業者に対してプラスチック製レジ袋の
無料配布を禁止し、有料化を義務化しました。
この制度により、使い捨て袋への依存を減らすとともに、
消費者にマイバッグやエコバッグなどの持参を促すことで、
日常の買物行動に変化をもたらす狙いがあります。
この取り組みは、単にレジ袋の使用量を減らすだけでなく、
私たち消費者が環境問題やプラスチックごみへの
意識を高めるきっかけにもなりました。
国民が買い物の際に「本当に袋が必要か?」と
一瞬立ち止まることこそが、
環境に優しい選択への一歩となっているのです。
制度の背景には、地球温暖化や海洋汚染といった
社会全体の課題への対応だけでなく、
プラスチック資源の浪費を抑制し、
限りある資源を賢く使う姿勢が求められた
意義も込められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 令和2年(2020年)7月1日から全国一律で実施 |
| 背景・目的 | プラスチックごみ削減、海洋汚染・地球温暖化への対応、ライフスタイル変革 |
| 制度の内容 | プラスチック製レジ袋の無料配布禁止、販売時に有料(義務化) |
| 消費者への影響 | エコバッグ・マイバッグの持参促進、使い捨てへの依存抑制 |
| 社会的意義 | プラスチック資源の適正利用と消費者意識の向上を併せて進める狙い |
レジ袋はどこでいくら?スーパーやコンビニでの価格と販売方法を比較
レジ袋の価格は、店舗ごとに異なりますが、
多くのスーパーやコンビニでは1枚あたり2円〜5円前後で設定されています。
【コンビニでのレジ袋価格】
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートなど大手チェーンでは、
共通して以下のような価格が採用されています:
-
S・Mサイズ:3円
-
Lサイズ:5円
どのコンビニでも、レジで購入の意思を伝えると追加できます。
サイズは店舗ごとに異なりますが、主に持ち手付きのプラスチック袋です。
【スーパーでのレジ袋価格】
イオン、イトーヨーカドー、ライフなど多くのスーパーでは、
レジ袋の価格は袋のサイズや素材によって変動します。
-
小サイズ(惣菜・お菓子など用):2円〜3円
-
中サイズ(日用品・生鮮品など):3円〜5円
-
大サイズ(まとめ買い用):5円〜7円
-
紙袋やバイオマス配合の袋:10円以上
スーパーによっては、バイオマス25%以上配合の袋を採用しているため、
価格がやや高めになるケースもあります。
【ドラッグストア・100円ショップ・ホームセンター】
ウエルシアやマツモトキヨシなどのドラッグストアや、
ダイソー・セリアなどの100円ショップでもレジ袋は販売されています。
-
多くは3円〜5円前後で、サイズ別に価格を変えている店舗が多いです。
【レジ袋の販売方法】
すべての店舗で、レジ袋はレジにて口頭で申し出て購入する形式です。
セルフレジの場合は、画面で「袋あり/なし」を選択します。
マイバッグを使用する人が増えているため、
店舗によってはレジ袋が目立たない場所に置かれていることもあります。
【ポイント】
-
価格は店舗の自由設定
-
袋のサイズ・素材で料金が変動
-
同じチェーンでも立地によって若干異なる場合あり
-
セルフレジ利用時は袋の購入選択を忘れずに
| 店舗種別 | サイズ | 価格(税込) | 素材・特徴 |
|---|---|---|---|
| コンビニ | S・Mサイズ | 約3円 | プラスチック製(薄手) |
| コンビニ | Lサイズ | 約5円 | プラスチック製(大) |
| スーパー | 小サイズ | 2円〜3円 | 通常のレジ袋 |
| スーパー | 中〜大サイズ | 3円〜7円 | 袋の厚みや用途で価格が異なる |
| スーパー | 紙袋・バイオ袋 | 10円〜 | 環境配慮型(店舗による) |
| ドラッグストア・他 | 各種 | 3円〜5円 | 店舗によってばらつきあり |
小売業や店舗ごとの販売価格と一律ではない理由
レジ袋の有料化は制度として全国的に実施されていますが、
販売価格は小売業や店舗ごとに一律ではありません。
これは、レジ袋の価格が政府や環境省から強制的に定められたものではなく、
あくまで事業者の判断で自由に設定できる仕組みだからです。
制度の背景として、環境問題への対応やプラスチックごみ削減を目的とした、
レジ袋有料化の義務化があります。
しかし、価格に関しては「有料であること」が条件であり、
金額の上限や下限は制度上定められていません。
そのため、大手コンビニでは一律3円や5円といった分かりやすい設定が多い一方で、
スーパーではサイズや素材に応じて2円〜10円以上と価格帯が分かれています。
たとえば、小型の袋を必要とする買物であれば2円程度で済む場合もありますが、
環境配慮素材(バイオマス配合)の袋を選ぶと5円以上することもあります。
また、地域ごとに事業者の対応や販売戦略が異なるため、
同じチェーンでも立地によって価格が違うことも少なくありません。
小売店が価格設定に自由度を持たせることで、
消費者の行動変容を促しつつ、資源削減や環境保全に向けた独自の取り組みを反映させやすくなっています。
つまり、価格の違いには単なる利益の問題ではなく、
店舗ごとの環境意識や素材選定・包装方針などが影響しているのです。
一律ではないことは混乱を招くこともありますが、
その分、消費者自身が買物の際に「どの袋を選ぶか」「持参するか」を判断するきっかけにもなっています。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 制度の仕組み | 金額は自由設定、義務化は「有料であること」のみ |
| 小売業の裁量 | 価格は事業者・店舗単位で決定可能 |
| 袋の素材やサイズ | バイオマス配合や大型袋は高め、小型袋は安価 |
| 地域差 | 同一チェーンでも地域・立地により価格差があることも |
| 環境配慮の取り組み | 店舗の方針により、袋の価格に環境への配慮や抑制効果を組み込んでいる場合あり |
| 消費者への影響 | マイバッグ持参やレジ袋不要の意識を促す工夫としても活用されている |
レジ袋の価格は1円未満でもOK?販売ルールの詳細
レジ袋の価格は1円未満で設定しても制度上問題はありません。
有料化のルールでは、義務化されたのは「無料で配布しないこと」であり、
具体的な価格や最低金額は定められていないからです。
つまり、0.1円や0.5円といった端数の金額でも、
「有料」であれば制度に適合しているとみなされます。
実際、一部の小売業や小売店では、1円未満の価格で販売している事例も確認されています。
制度の目的は、レジ袋の使用量を抑制し、
プラスチックごみや海洋汚染といった環境問題の対策を促すことにあります。
ですので、有料化という行動変容のきっかけさえ提供できていれば、
価格の大きさそのものは問われていません。
ただし、極端に低価格な設定では、
消費者に「実質無料」と感じさせてしまう場合もあり、
制度の趣旨に合わないと批判を受ける可能性もあります。
そのため、多くのスーパーやコンビニでは、
消費者に有料化を明確に認識してもらえるよう、
3円〜5円といったわかりやすい価格で販売する傾向にあります。
販売価格の設定は、事業者の裁量にゆだねられていますが、
その価格が環境への配慮を伝えるシグナルとなるため、
制度を形だけでなく、意味のあるものとして運用するための工夫が求められます。
なお、販売価格の表示方法にも一定の配慮が必要です。
税込価格での表示や、レジでの明確な伝達を通じて、
消費者が「レジ袋は有料である」と認識できることが、
制度の実施上の大きなポイントとなっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1円未満の設定 | 制度上は可能。有料であれば金額に制限なし |
| 価格の自由度 | 小売業や店舗ごとに設定自由。義務は「無料配布の禁止」のみ |
| 制度の目的 | レジ袋の使用削減とプラスチックごみ対策 |
| 実質無料の懸念 | 極端な低価格は制度の意義を損なう恐れあり |
| 主な価格帯 | スーパーやコンビニでは3円〜5円が主流 |
| 表示ルール | 消費者にわかりやすく表示することが望ましい |
| 意識への影響 | 販売価格は、環境問題への取り組み姿勢を伝える手段でもある |
レジ袋の有料化制度はどの法律で定められている?政府・省庁の対応を解説
レジ袋の有料化制度は、正式には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
、通称「容器包装リサイクル法」に基づいています。この法律の関連省令が改正され、
全ての小売業や小売店に対し、プラスチック製買い物袋の無料配布を禁止し、
有料での提供を義務付ける内容が規定されました。ELEMINIST+3京都市+3オリカネ+3オリカネ+4経済産業省+4株式会社ファー・イースト・ネットワーク+4
この制度の導入は、2019年5月に政府が策定した「プラスチック資源循環戦略」の一環として、
ごみの排出抑制やプラスチックごみ削減の取り組みの柱に位置づけられています。経済産業省+2産廃メディア|廃棄物処理事業者向け総合情報サイト+2
関連省令の改正は2019年12月27日付で行われ、制度の根拠が明確になりました。京都市
制度の趣旨を受け、経済産業省と環境省は共同でガイドラインを策定し、
小売事業者への対応指針を策定しています。これにより、店舗がどの袋を対象とし、
どのように消費者に提示すればよいかが整理されました。株式会社ファー・イースト・ネットワーク+8経済産業省+8オリカネ+8
このように、レジ袋の有料化は法律に明確な根拠を持ち、政府が制度設計からガイドライン策定、
そして実施支援に至るまで一貫して対応している点が特徴です。私たち消費者もこの制度を理解し、
マイバッグなどの工夫を通じて環境への配慮を日常に取り入れることが求められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) |
| 制度の内容 | プラスチック製買い物袋の無料配布を禁止し、有料提供を義務化 |
| 改正時期 | 2019年12月27日に関連省令を改正 |
| 対応責任省庁 | 経済産業省・環境省がガイドラインを共同で策定 |
| 目的・背景 | プラスチックごみ削減、レジ袋使用量の抑制、消費者の買い物行動変容を促す |